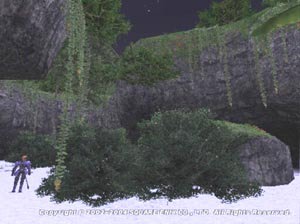| その297 キルトログ、ビビキー湾を観光する(2) 私は夕照桟橋にいる。仲間たちは魔行船に乗って、プルゴノルゴ島へ出発してしまった。「Kiltrogさんがあ、Kiltrogさんがあ」というGelgelの声が聞こえる。だがこれは仕方がない。自分で巻いた種なのである。それにしても、人だかりで船の入港にも気づかないとは、何という間の抜けた話であろう。 桟橋に立っている係員に話を聞いた。次の便が来るまで6時間もある。しかしながら、これはマリヤカリヤリーフ――ガイドの説明によれば、世界一のさんご礁――を遊覧し、戻ってくる便なので、乗っても仕方がない。まあプルゴノルゴに出発するまで、更なる6時間を効果的に潰せはするだろうが、この冒険者の人込みをかき分けて、チケットを買い直す自信は、私にはない。仲間が島で待っている。今度の船はどうしても逃すわけにはいかないのだ。 待つこと半日。ようやく、魔行船が姿を現した。折りしも日が暮れかけて、大きく風を受けた帆布が、鮮やかなオレンジ色に染まっていた。冒険者がどかどかと乗り込んでいく。桟橋の舳先に立っている係員は、のんびりしたようでいて、しっかりチケットをチェックしており、無賃乗船は容赦なくつまみ出されるそうだ。私はふところを覗き、間違いなく券を買っていることを確かめた。そうしてようやく気持ちを落ち着け、筏の上にどっかりと座り込んだのだった。 やがて魔行船が、ゆっくりと水上を滑り出した。潮風がつんと鼻を刺した。波しぶきが霧になって、降りかかるのが気持ちいい。大勢の乗客も、めいめいに波の景色を楽しんでいるようだ。そのうちの一人に、見慣れたヒュームの女性がいた。「Liryuan」と私は声をかけた。「何という奇遇な」 Liryuanは私の古い友人である。彼女も仲間と一緒に、プルゴノルゴ島へ向かうところだった。船が到着するまで、私たちは、景勝地としての島について話した。 目的地に到着するころ、「頑張って」と手を振り合ったのだが、思えば妙な挨拶である。観光地で何を頑張るというのか。偶然にも私は、ギルドのタルタル君の言う「話し合い」を控えているわけだ。それも相手は、罠用のモンスターを配置して、ギルド員にけしかけるようなやつである。 腹をくくっておく必要がありそうだ。私が意を決したころ、船頭のミスラが、島への到着を声高に告げた。
既に日は沈み、夜もふけていたが、砂浜と海の溶け合う様子は、もし昼間に見たなら、どんなにか美しいだろうと思わせた。しかし私には、周囲の景色を楽しむ間はなかった。Leeshaが岩陰で手招きをしている。「そうだ」と私は言った。「島の中心とは、いったい何処なのだ」
そこで地図を開いてみた。幸い、ビビキー湾とは別枠に、プルゴノルゴ島の地形が拡大されていた。この島は南北に細長い形をしている。私が着いたのは北端の港だった。中央に山の絵があり、トコペッコ山と書かれている。私は南に目を向けた。シダの林の向こうに、頭を突き出しているのがそうであろう。ということは、山を目印に向かえばいいわけだが、まっすぐに道が続いているわけではない。どうやららせん状に、ぐるぐると走っていかねばならないようなのだ。面倒な話だ。 私とLeeshaは、仲間たちの背中を追って走っていった。ところどころで、岩が大きなアーチを作っており、ツタがカーテンのように垂れ下がっていた。いいかげん走り疲れて、どっちが北だか南だかわからなくなりだしたころ、丸い広場に行き当たった。真ん中には、横たわった鯨を思わせる岩があった。さてここが、約束の場所なのだろうか。中央に山があるからには、てっきり山頂での話し合いになるのかと思っていたが。
「あっ!」と誰かが声をあげた。「来る!」 私は反射的に、背中の槍をひっつかんで身構えた。岩陰から、全身が墨のように黒い、マンドラゴラのような生き物がぞろぞろ出てきて、私たちに攻撃を始めた。6,7匹はいただろうか。きっと例の、狭量の話し相手が仕掛けた罠に違いない。 私たちが本気で応戦すると、ピーリフールの陣形はあっさりと崩れた。私とLeeshaだけではとても歯が立たなかったろう。だがこちらは10人以上もおり、少なくとも1名は除いて、精鋭ばかりが集まっていたので、労せずして殲滅することが出来たのだった。 砂の上に小さな窪みがあった。私はおやとしゃがみ込んだ。紙の切れ端のようなものが、穴から覗いていることに気づいたからだ。こっそりと引きずり出してみた。丁寧に巻かれた羊皮紙である。封の回りを調べてみて、「契約書」と書かれているのを発見した――島の契約書だ。話し相手が落としていったのだろうか? このまま置いてはおかれない。周囲に見られないように、私はそれを、背負い袋に押し込んだ。 戦闘が終わって一息ついていると、ぎちぎちぎち、と、紐を固く締めるような、おかしな音がした。どうも岩陰から聞こえたような気がする。私はそちらに目をやった。それから、手甲を外し、両瞼をごしごしと擦り、もう一回見つめた。いる筈のないもの、ある筈のないものが見えたのだ。オークの人力戦車が、繁みの向こうに立っていたのである。 戦車の姿は消えていなかった。私が夢を見ていたり、幻術をかけられているのでないとすれば、まぎれもなくこれは現実なのだ。戦車と私の目が合った――こういう言い方は妙だ――要するに、顔の部分と向き合ったのだ。中にいるのが誰であれ、彼または彼女は、戦車ののぞき穴から、私が見つめていることには気づいたはずであった。 戦車は、再びぎちぎちと音を立てて、ゆっくりと姿を消した。
港に戻るとき、Leeshaがある発見をした。屋根のようにせり出した岩の下に、一体のオーク戦車を見つけたのだ。私たちは近くまでいって、ばしばし車体を叩いたり、ブーツで蹴飛ばしたりしていたが、全く反応がない。抜け殻なのか、あるいは、相当忍耐強い人物が入っているのか。 いずれにせよ、この戦車は敵ではないようだ。むろん中の人物が、ギルドに敵対している可能性はあるが、少なくともゲルスバで襲撃してくるようなタイプとは違う。オークが揃って入っているとは考えにくい。 ならばなぜ、こんな戦車が、よりによってミンダルシア大陸の、それも辺境の島に存在するのだろうか。どう考えても合理的な説明はつかないように思え、私たちは、しきりに砂浜の上で首を捻るのだった。 (04.10.05)
|