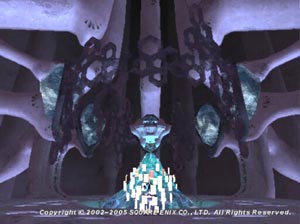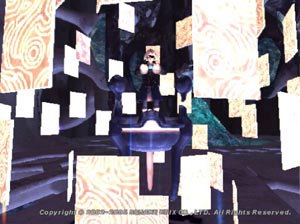| その424 キルトログ、最終決戦に臨む(2) 「ぼくを怒らせたことを、後悔するんだね」 エルドナーシュが言い放ち、両の手のひらを前に突き出した。手のひらの先に、長方形の小さなパネルが現れた。奴がそこに触れると、クリサリスのような機械が、甲高い音を立てながら、空中を滑って前進してきた。エルドナーシュと機械の周囲には、無数の長方形のパネルが、互いに距離を保ちながら浮かび、さながら卵の殻のように、魔王子を遠巻きに包み込んでいる。
エルドナーシュの傍らに、灰色の球体がふたつ、ふよふよと旋回していた。パネルが壁であるとすれば、どうやらふたつの玉は、敵を攻撃する守護者の役目を果たすようだ。見たところこれも機械らしい。厄介な装置である。Steelbearのスリプルが効いてくれればよいのだが……。 エルドナーシュの攻撃が始まるまで、少し時間があった。すぐさま飛びかかりたいのを耐えて、我々も万全の体勢を整えた。ソールスシを頬張った。空蝉の術を唱えた。睡眠攻撃に備え、忘れないように服毒した。念のため、Ragnarokから預かったリレイズゴルケットを使って、いざというときに復活できるよう準備をした。 Steelbearが、私やLibrossにヘイストをかけてくれた。Sifが私たちの傍らに来て、弦をかき鳴らした。「進軍の調べ!」彼の歌声を聞いていると、身体の奥底から、力がみなぎってくるようだ。LibrossもParsiaも既に準備を終え、じっと私の合図を待っている。 私は、ジャガーノートを軍配のようにうち振るった。 「突撃!」
総員、鬨の声を挙げて襲いかかった。玉が前に進み出てきた。Parsiaが殴りつけられたものの、玉はSteelbearのスリプルでおとなしくなり、もう一体もスリプル2で動きを止めた。今のうちにエルドナーシュを攻撃するのだ。私は奴を挑発して、パネルぎりぎりまで近づいた。一枚一枚には不思議な文様が浮かび、自ら黄白色の光を発して、さながら呪符のように見える。隙間から、エルドナーシュが魔法を唱えている様子が伺えた。さっそく斧で斬りかかるのだが、リーチが届いたと思っても、生身の肉体を捉えている感覚はなく、何だかがきんと音がして、固い岩に跳ね返されているような印象なのである。 私は悟った――このパネルは、大きく間隔が空いているようで、隙なく王子を守っているのだ。まずはこちらを何とかせねばならぬ。 私たちは、標的を切り替えた。斧や剣や拳で、斬りつけ、殴りかかり、強引に壁をこじ開けにかかった。そのうち不思議なことが起こった。エルドナーシュを中心にして、壁全体がくるくると回転を始め、放射状に広がり始めたのである。 私たちは身を固くした。スピードに乗ったパネルが我々を襲った。それは分身にぶちあたり、刃物のような鋭さを見せて、根こそぎ切り裂いてしまった。壁はやがて収縮を始め、再び元の位置に戻っていった。何ということだ。このパネルは防護壁であるうえ、頼もしい武器にもなるのだ。後にわかったのだが、機械から繰り出されるウラノスカスケードは、ダメージを与えるだけではなく、我々を痺れさせ動けなくさせる、バインドの効果も持っているらしい。 Leeshaがサイレスを唱え、エルドナーシュを沈黙させようとしたが、奴は右手を振っただけで、魔法を弾いてしまった。奴はトルネドを唱えた。壁の奥から、小さな竜巻が吹き起こり、私にぶつかってきた。分身が再び、風でばりばりと剥がされてしまう。私はぞっとした。こんな魔法をいくつか食らったら、いくら体力自慢のガルカでも、ひとたまりもないだろう。攻撃する時間を削ったとしても、空蝉の術は決して欠かさぬようにせねばならぬ。 エルドナーシュが、後衛のもとへ進んでいこうとした。私は奴を挑発した。同時に反対側に走り出し、奴がもといたポジションまで誘導した。機械が繰り出すウラノスカスケードや、ガイアストリームに、後衛を巻き込んではならない。一方で私たちが、ケアルが届かない位置に立ってしまってもいけない。Librossが私の左、Parsiaが右について、再び武器を振るい始めた。しかしながら、斧に伝わる感触は、いまだに岩のようで、この堅固な壁を破るには、まだ相当な時間を要するだろうと思われた。 こうなったら持久戦だ。 私がその覚悟をした時である。パネルが眩しい光を放ったかと思うと、ひときわ鋭く回転を始め、先ほどとは比較にならぬ速さで斬りかかってきた。その輪は私たち前衛どころか、離れたところにいるLeeshaたちも容赦なく巻き込んでいく。 「うわあ!」 強烈なフェイズシフトが、我々の体力を奪った。Leeshaがケアルに追われ始めた。時わるいことに、灰色の玉が睡眠から覚め、再び動き出した。ふよふよとSteelbearを攻撃に行く。Leeshaの手助けをするはずの彼は、玉の対応に追われた。再び眠らせようとするが、攻撃されているのでなかなかうまくいかない。彼が何とか寝かしつける間に、Parsiaがケアル4をかけてくれた。彼女はナイトだから、白魔法をいくらか使えるのだ。エルドナーシュが彼女に向き直った。ただの戦士である私より、回復術を持つ相手から片付けようと思ったに違いない。 機械がぶんと唸りを上げた。パネルが回転を始め、クロノスリング・シータが襲いかかってた。Librossは分身を飛ばされただけだが、私とParsiaは思い切り身体を打たれ、顔をしかめた。彼女は怯まず、岩のような防護壁に向かって、スピリッツウィズインを叩き込んだ。文字通り魂の一撃なのだが、それでも破れる様子はなかった。何という硬さ! 私は再び挑発をして、エルドナーシュを釘付けにした。Librossのパンチが炸裂する。がきん、がきんと無機質な音が響くが、このとき、徐々に硬度が弱ってきているのがわかった。やはり、我々の狙いは正しかった。このまま続ければ、壁をこじ開けられるのだ。機械さえぶっ壊せば、直接エルドナーシュの脳天をかち割ることが出来る! フェイズシフトが襲ってきた。我々は避けきれず、旋風に巻き込まれた。頑丈なホーバージョンに包まれていながら、全身に激痛が走った。明らかに先刻よりも、技の鋭さが増している。どうやらフェイズシフトというのは、徐々に破壊力を上げてくるようだ。ただでさえ後衛に混乱が巻き起こっている。私は考えた……次に食らったらどうなる? そして、すぐさま迷いを打ち消し、空蝉の術を唱えた。その前に片付けるのだ。全力で攻撃すれば、決して不可能なことではない。 私は咆哮を挙げた。ウォークライ! Librossが身構えた。彼は高らかに声をあげながら、体重を乗せた拳を、壁に向かって勢いよく叩き付けた。 「夢想阿修羅拳!」
Librossはいつか語ったことがある。彼はその技を、バストゥークにいる拳闘家、ガルカのオグビィから受け継いだのであると。 かつてのミスリル銃士、ヒュームのコーネリアは、オグビィの一番弟子だった。彼女は優秀なモンクだったが、ついに師の最終奥義を継承することはなかった。愛するラオグリムを守るために、自ら身体を投げ出して、裏切り者の凶刃に倒れたのだ。 その無念は今、LibrossやLandsendのような冒険者に託された。魂の宿った拳は、一度に8回敵を打つという、信じられぬスピードを可能にした。彼の立て続けのパンチを受けて、壁が鈍い音を出し、軋み始める。私もそれに続いた。ランページ! 両手に持った斧――RuellとRagnarokの思いが乗った斧。Librossと同じ箇所を狙い、私は5度、正確に攻撃をヒットさせた。 もう一息だ。もう一息で壊れるはずだ。 しかし、異変を感じたエルドナーシュも、黙ってはいなかった。彼は素早く機械をあやつって、クロノスリング・ラムダを繰り出し、私とLibrossの分身を吹き飛ばした。次いで、ういん、ういんと高まる音。フェイズシフトだ! 避ける術はなかった――1度目、2度目とは比べ物にならぬほどの衝撃が、我々を急襲した。全身を強く打ったとき、死んだ、と思った。だが、壁が収縮してしまっても、私はまだ立っていた。息をしていた。生まれてかつてこのときほど、自分の頑丈さに感謝したことはない。 Parsiaの剣が、大きく波打ちながら、振り下ろされた。落雷のような激しい音がした。衝撃に彼女は思わずひるみ、尻もちを付きそうになった。アッ、と私は声を挙げた。パネルが明滅している! やがてそれは、狂ったようにちかちかと瞬きを繰り返し、空中にかき消すように見えなくなった。我々はついに防護壁を破ったのだ! だが、エルドナーシュは冷静だった……奴はクエイクを唱えていた。私は斧を振るい、魔法をやめさせようとしたが、遅かった。私の武器は空を斬り、奴は詠唱を終えた。もしかしたら笑っていたかもしれない。その片目はまっすぐに、ある人物を見つめていた――バリアにとどめをさした女ナイトを。 Parsiaの立っていた地面が、大きく震えた。彼女は跳ね上がった。Parsiaは心臓を押さえ、喉から息をこぼして、地面に崩れ落ちた。瀕死の状態ではひとたまりもなかった。断末魔の声はなく、彼女はそれきり、糸が切れた人形のように動かなくなった。 その向こうで私は、灰色の玉が、蛍みたいに旋回するのを見た。床に誰かが倒れていた。ふたつの玉は、弔うように舞っていた……ガルカの赤魔道士、Steelbearの冷たいむくろの上を。 (05.02.03)
|